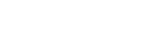山岳ガイド真鍋貴彦は公益社団法人日本山岳ガイド協会山岳ガイドステージⅡ(No.1106)、スキーガイドステージⅡ、自然ガイドステージⅡに認定されており認定範囲の範疇でガイド業務を行います。(ガイド対顧客標準人数比率に係る規定![]() )
)
日本国内で季節を問わず全ての山岳ガイドおよびインストラクター行為を行うことができる。但し、スキーガイド分野は別に資格を取得する。登山ガイドステージⅡの範囲に準じる。
ピッケル、アイゼン、ロープなどを使用せず登高できる雪山で、ゲレンデや、一般交通路に隣接しないエリアでのスキー・スノーボードガイドを行うことができる。この資格は登山ガイドステージⅡ、山岳ガイド資格の付帯資格となる。<活動エリア>登山ガイドステージⅡの範囲に準じる
国内で、四季を通じて、人間社会と隣接する里地・里山・山地・高原において自然、歴史、民俗等を開設する自然ガイド行為を行う事ができる。※自然ガイド単独資格者は、ピークハントが主たる目的となる登山ガイド業務は、行ってはならない。
無積雪時期の高原、山野、里地里山。および積雪期の里地里山。高原、山野は、森林限界を越えない範囲とする。

申込金については当社Q&Aにてご確認をお願いします。
| 拘束料金 |
ガイドをさせていただく際の基本的な価格(日当)です。拘束時間は目安6時間~7時間程度となります。 無積雪期30,000円~/1日、積雪期40,000円~/1日 ※料金は税抜表示です。 |
|---|---|
| ルート料金 | 株式会社昭文社発刊の山と高原地図の破線または実線がない登山道の場合発生します。また岩登り(岩壁または岩稜)、縦走時の難易度により発生します。料金は別途お問い合わせをお願いします。 |
規定のページをご確認ください。
その他のページをご確認ください。
![]()
外岩を開拓したライン通りに登ることを基本に、クライミングフォームの大切さを学んでいただきます。不要なパワーを使わず体の柔軟性を利用したクライミングを目指し、腕力だけに頼らずしなやかに登るためのフォームを維持出来るようトレーニングしていただきます。「バランスを意識したポジションによる登り方」をスクール生の立場にあった内容で丁寧に解読を行い説明します。当スクールはフリークライミンググレードである5.11a~bクラスを、スクール生自身リードクライミングが行えるようになる事を最終目標としています。そのため、まずは確保技術(トップロープの確保⇒リードの確保)、そして登攀能力を上げるために初期段階では5.7~5.10前後を繰り返し、トップロープを利用して基本的な体さばき、手さばき、足さばきを学びます。テンションをかけず安定したフォームで登れるようになればマルチクライミング(大きな岩場雪彦山地蔵東稜または三峰東稜、御在所岳前尾根等)に出かけていただきます。また、道場周辺の岩場でさらにフリークライミンググレードを上げて5.10前半~5.11までを同様にテンションをかけず安定したフォームで登れるようになればレベルアップしたマルチクライミング(御在所岳中尾根または小豆島橘の岩場(拇岩)赤岩のクラック)、にチャンレンジしていただけます。順調にいけば5.10前後のリードクライミングにチャレンジできます。雨天時は古典的なエイドクライミング、レスキュー等も行い、全ての技術を身に付けていただければ自立したリードクライマー誕生となります。期間は半年間~1年間程度必要です。ディフェンス(defense)クライミング(直訳:防御防衛しながら登る)、オフェンス(offence)クライミング(直訳:攻撃しながら登る)、を繰り返し行っているのがクライミングです。安全で怪我をしないリードクライマーの育成には少しお時間はかかりますが得られた技術、体力は一生のものです。
クライミングそのものを上達させるためには登ることはもちろん、確保の経験数も必要になってきます。当スクールでは道場周辺であれば一日平均ルート10本程度を目安に登ります。ただしスクール生は入校~1ヶ月程度は2本~4本、2ヶ月~4ヶ月程度は4本~6本、4ヶ月~6ヶ月程度で6本~8本のペースで登ります。そして一年間経過すると10本程度登れるような体力、技術が身につきます。また、クライミングに必要なウェイトトレーニング、栄養学についても知識を持っていますので興味があれば現場にてお聞きください!
お問い合わせフォームから別途ご相談ください。
最新の開催日程・内容詳細については、日程カレンダーをご確認ください。
| クライミングスクール | クライミング体験 | |
|---|---|---|
| 日 程 | 基本的に土・日・祝日開催(リクエストがあれば平日も可。ただし、最低催行人数以上で開催)。 |
基本的に土・日・祝日開催(リクエストがあれば平日も可。ただし、最低催行人数以上で開催)。 |
| 定 員(最小開催人数2名) | 1~5名 |
1名~5名 |
| ガイド料金 | お一人様:16,000円 |
お一人様:10,000円(2名以上の場合は下記の表をご確認ください) |
| キャンセル料 | 当社規定通り |
当社規定通り |
| その他 | 天候の判断は当社規定通り |
天候の判断は当社規定通り |
※表示価格は全て税抜き価格です。保険料は別途頂きます。
JR道場駅周辺の岩場(不動岩、烏帽子岩、駒形岩)でマンツーマンでクライミングを深く学びたい方、ヘルメット、ハーネス、クライミングシューズを購入された方、クライミングウォールで物足りない、外岩のクライミング希望の方などは、ぜひご利用をお勧めします。
| 1名 | 18,000円~ |
|---|---|
| 2名 | お一人様 16,000円~ |
| 3名 | お一人様 14,000円~ |
| 4名 | お一人様 12,000円~ |
| 5名以上~ | お一人様 10,000円~ |
※表示価格は全て税抜き価格です。
規定のページをご確認ください。
その他のページをご確認ください。
1. 保険の期間
原則、毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後24時00分まで。
フィールドアドベンチャー山岳保険事務局より12月1日現時点の会員顧客様に次年度更新手続きとして保険料の請求書発行を行い、お支払完了次第次年度の会員証及び保険証券番号をご連絡します。なお、次年度更新手続きに記載されている期日以外にお支払をされた場合、始期は遅くなる(終期は同じ)可能性があります。
2. 保険の種類
下記、2種類の保険を掛けています(但し会員顧客様に保険料を負担して頂いております)。
- (A)スポーツ安全保険(契約者:公益財団法人スポーツ安全協会 保険会社:東京海上日動火災保険株式会社)
- (B)山岳共済会の山岳遭難・捜索保険(契約者:日本山岳協会山岳共済事務センター 保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
3. 保険の内容
下記、2種類の保険を掛けています。
- (A)スポーツ安全保険(加入区分は「D」)。詳細は(公益財団法人スポーツ安全協会)ご確認ください。
- (B)山岳共済会の山岳遭難・捜索保険。詳細は(日本山岳協会山岳共済事務センター)ご確認ください。
1. 保険の期間
原則、登山引受日の当日午前0:00~3泊4日(日帰りであっても期間は3泊4日です)とします。
顧客はフィールドアドベンチャー山岳保険事務局から指定期日までに保険料の支払いを行います。損害保険料のお支払いが確認できない顧客は、参加引受不可となり顧客自身の自己都合キャンセルとなります。
2. 保険の種類
(A)普通傷害保険(団体契約者:有限会社フィールドアドベンチャー 保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
3. 保険の内容
加入前に保険料及び補償内容を必ずご確認下さい。
万が一ガイドツアー参加時に怪我及び事故が発生した場合、当社ではガイドが怪我の応急手当を行い、警察署・消防署の通報、病院及び搬送(ヘリコプターによる搬送含む)の遭難救助依頼を行います(事故状況にもよりますが通報、遭難救助依頼を行なわない場合もあります)。
1. 顧客自身が加入されている健康保険証を利用させて頂き、病院及び薬剤局のお支払いを行います(健康保険証の持参がない場合は全額自費治療となり高額なご負担となります)。
2. 顧客の損害賠償請求金額(治療費等及求償)に従い、当社が加入している賠償責任保険で対応します(但し、請求金額の内容によりますが賠償責任保険でご対応出来ない場合もあります)。
レンタル料:2,000円/1日
レンタル料:2,000円/1日
セット料金:5,000円/1日
単品:ヘルメット2,000円/1日・ハーネス1,000円/1日、クライミングシューズ2,000円/1日
3,000円/1日
レンタル料:1,000円/1日
- ※お届けの場合は送料が別途必要です。ご利用日の翌日にご返送ください(送料の負担が必要)。
- ※数に限りがありますのでお早めにお申込みください。
※表示価格は全て税抜き価格です。
- ザック(個人のお荷物がすべて入るもの)
- 40l~60l、雨具
- 防寒衣(ダウンジャケット可)
- ヘッドライト(ルーメン数以上)
- 登山靴(積雪4シーズン対応、無積雪3シーズン対応、沢登り遡行の場合は沢靴)
- 常備薬
- 水筒(寒冷期は保温水)
- 昼食(行動食)
- 非常食(1食)
- 地図
- コンパス(方位磁石)
- 手袋
- 帽子
- ナイフ
- 個人食器
- タオル
- ゴミ袋
- 日焼け止め
- 洗面具(入浴予定の場合は入浴用品)
- ティッシュペーパー(水溶性)
- 着替えなど
- シュラフ
- エアーマット
- 個人食器類
- 宿泊する日数の食糧(朝食、夕食)
- ピッケル
- アイゼン(10本爪以上)
- オーバージャケット
- オーバーズボン
- ロングスパッツ
- 防寒手袋
- 防寒着(ダウンジャケット)
- サングラス(ゴーグル)
- 雪山用アンダーウェア
- 帽子、目帽子など
- ヘルメット
- ハーネス(レッグループタイプ)
- クライミングシューズ
- カラビナ(ノーマル8枚、HMS3枚、D環2枚)
- 確保器
- 下降器
- スリング(60cm×3本、120cm×2本)
- ヘルメット
- ハーネス(レッグループタイプ)
- 沢靴
- カラビナ(ノーマル8枚、HMS3枚、D環2枚)
- 確保器
- 下降器
- スリング(60cm×3本、120cm×2本)
当社は白山書房発刊の「アイスクライミング 全国版」「改定増補 アイスクライミング」「日本の岩場(上)(下)」白水社発刊の日本登山大系、山と渓谷社発刊の日本100岩場、平成22年7月一般社団法人日本旅行業協会/一般社団法人全国旅行業協会/公益社団法人日本山岳ガイド協会作成等の資料を参考にガイド料金及び参加レベルを総合的判断に行っております。
各山域解説は、概念、クライミング・コンディション、ベース、アプローチ、下降路の淳で解説してある。アプローチ、下降路に関しては最も一般的な経路を解説してあるが、各岩場独自のもの(例えば滝谷のような)についてはルート解説を参照されたい。なお、この解説は基本的に夏(春~秋)期のものであり、冬期に関しては触れていない。
ルート解説文冒頭の〔4級Ⅳ、A1 230m 3~4時間(例)〕という表示は、ルートグレード4級、ルート中最難ピッチグレードがフリーでⅣ、人工でA1、登攀距離(ロープがのばされた長さであって、高度差などではない)230m、取付から終了点までの通常登攀所要時間3~4時間、ということをあらわしている。
また、ルート名に並ぶ星印はそのルートの推薦基準を表している。これは特にポピュラー度を考慮してつけてあるが、あまり登られていなくても優れたルートは相応の価をつけてある。
年月日、氏名はそのルートの初登、冬期初登、フリー化などを、可能な限り調査した上で記載したものである。なお、記述が無いからといって冬期未登あるいはフリー未登とは限らない。
ルート図は主に取付から終了点までを表示してある。概ね実際の形状にそって作図してあるが、わかりやすくするために誇張や略式記号を使用してある。略式記号については以下の通り。
なお、アメリカンエイド・グレードはAAで示してある。(後述)
| 穂高岳 | 谷川岳 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | 前穂北尾根 |
東尾根 |
|
| 2級 | 3峰フェース登高会ルート |
剣岳本峰南壁 |
|
| 3級下 | 滝谷ドーム北壁 |
二ノ沢本谷 |
チンネ中央チムニー |
| 3級 | 滝谷ドーム中央稜 |
中央稜 |
チンネ左下カンテ |
| 3級上 | 滝谷クラック尾根 |
南稜 |
Dフェース富士山大ルート |
| 4級下 | 屏風岩東稜 |
中央カンテ |
チンネ左稜線 |
| 4級 | 屏風岩雲稜ルート |
変形チムニー |
源治郎Ⅰ峰上部フェース |
| 4級上 | 屏風岩鵬翔ルート |
コップ左岩壁 |
甲斐駒赤石沢Aフランケ赤蜘蛛 |
| 5級下 | 屏風岩緑ルート |
衝立岩雲稜ルート |
丸山南東壁塚田=小暮ルート |
| 5級 | 屏風岩右岩壁ダイレクト |
衝立岩A字ハング |
唐沢岳幕岩広島ルート |
| 5級上 | 屏風岩マニアック |
幽ノ沢中央壁実践ダイレクト |
明星山P6フランケ左壁 |
| 6級上 | 屏風岩ブッシュ・ド・メメケ-ル |
奥鐘山西壁OCCルート |
|
| 6級 | 屏風岩パラノイア |
衝立岩不思議ロード |
奥鐘山広島ルート |
| 6級下 | 屏風岩フリーフォール |
奥金山近藤=吉野ルート |
| フリークライミング | 人工登攀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デシマル | 残置支点をたどるもの | アメリカンエイド | ||||
| Ⅰ | まったく易しい |
A0 | ピトンをホールドとする動作 |
墜落想定距離 | ||
| Ⅱ | 三点確保を要す |
AA1 + |
0~2m |
|||
| - | やや難しい |
|||||
| Ⅲ | 5.0 |
ロープによる確保が必要 |
||||
| + | 5.1 |
A1 | 支点が確実で動作も難しくない |
AA2 + |
6~7m |
|
| - | 5.2 |
難しい |
||||
| Ⅳ | 5.3 |
やや高度のバランスを要す |
||||
| + | 5.4 |
AA3 + |
10~20m |
|||
| - | 5.5 |
非常に難しい |
||||
| Ⅴ | 5.6 |
高度なバランスを要す |
A2 | 支点、動作のどちらかが不確実 |
||
| + | 5.7 |
AA4 + |
25~40m |
|||
| - | 5.8 |
極度に難しい |
||||
| Ⅵ | 5.9 |
極度に微妙なバランスを要す |
||||
| + | 5.10a |
A3 | 支点が不確実で動作も難しい |
|||
5.10b |
AA5 + |
50~100m |
||||
5.10c |
||||||
5.10d |
||||||
5.11a |
||||||
クライミングにおけるグレード(等級)とは、そのルートを他の沢山のルートと比較して難しさを評価したものである。勿論、“難しさ”と一口にいってもその内容は様々で、人によっても見方は違い、あくまで主観的評価の域を出ない。本編のグレード・システムも出来るだけ客観的な強化に近づくべく多くのルートを経験しているクライマー諸氏の意見を参考にしているが、やはり完璧なものではない。また、 グレードは用具や登山思潮の変化など、その時代によっても変化するものであり、そうした意味からも絶対的なものとして盲信することなく、内容をよく把握して利用していただきたい。
ピッチグレード
ルートを構成する各ピッチの技術的な難しさを評価したものである。その前提となる自然条件は「夏季、乾燥」の状態である。
フリークライミングにおいてはRCCⅡ体系のⅠからⅥまでが通常使われているが、Ⅴ、Ⅵ以上の難度についてはデシマル(5.9、5.10・・・)も併用されている。これはⅦ、Ⅷに置き換えることも可能であり、一時そうした表記がされたこともあったが、現在では高難度、特に5.8以上の難しさではデシマルの方がわかりやすくなっているため、このままにしてある。
人工登攀においては従来通りの残置支点(ボルト、残置ピトン等)をたどるものは支点の効きや傾斜によってA1、A2、A3を、残置支点を使わずに自分でピトンを打ったり、ナッツ、フレンズ、スカイフックなどに頼って登る、いわゆるアメリカンエイドに関しては墜落想定距離によってAA1、AA2、・・・AA5を使用している。しかしこのアメリカンエイドグレードはボルトが打ち足されるなどによって残置支点が付け加えられれば、当然その意味はなくなり、グレードも大幅にダウンすることになる。今後この手のルートを再登するにあたってはそのようなことのないようお願いしたい。
ルートグレード
そのルートを難しくする要因を総合的に比較し、評価したものである。1級から6級までに分かれ、6級が最も難しい。現在の6級を越える難しさということで今後7級という概念も導入可能であるが、日本の岩場のスケールや習慣から、現在の6段階が最も妥当と思われる。
ルートの難しさを決定する要因は次のようなものである。
- ①スケール(登攀距離、所要時間、傾斜度)
- ②技術的難度(ピッチグレード、難しさの連続性や多彩さも加味される)
- ③確保条件(ビレイポイント、プロテクションの良し悪しと量)
- ④岩の状態(脆い、堅い、濡れている、草付が多い等)
- ⑤ルートファインディングの良し悪し
- ⑥エスケープルートの有無および退却のしやすさ
- ⑦アプローチ、下降路の難易(主にも最寄の安全圏から)
- ⑧自然条件(標高、方位、岩場の安定性、安全圏からの距離等)
以上のようなことを比較判断してルートグレードは決められるわけだが、本編のグレードシステムを利用する際は次のことにも注意して欲しい。
まず、グレードは(そのルートを余裕を持ってこなせるということが理想だが)そのルートを能力ギリギリで登れるというレベルのクライマーがルート選択の手がかりにする、ということも考えてグレーディングしてある。これは墜落やルートファインディングのミスなど技術的な失敗もありうるということを前提にしているということで、失敗に対する許容度が低い(プロテクションが悪い等)ルート、危険なルートはスケールや技術的難度の割に高めにつけてある。(一ノ倉沢南稜フランケ等)
同じような意味から、比較的新しいルート、あまり登られていないルート、ルートファインディングや残置支点に疑問が残る場合も、グレードは高めにつけてある(甲斐駒Aフランケ、北岳バットレス第2尾根等)。
アメリカンエイドルートに関しては、そうした技術がまだ一般的に広く浸透していないので、同じグレードでもボルトラダーのそれとは比較しにくい。特殊技術が必要とされるということで、現時点ではグレードは高めにつけてある(屏風岩東壁マニアック、丸山南東壁Appendix等)。
グレードを利用する上で難しいのが、違った山域、違ったエリア間の比較である。例えば滝谷クラック尾根と一ノ倉沢南稜では同じグレードでもアプローチその他の労力に雲泥の差がある。しかし、ここでは安全圏内の諸条件(例えば上高地~北穂間の労力、時間など)は出来るだけ度外視した。しかし前穂東壁右岩稜のように至近の安全圏(北尾根3・4のコル)からのアプローチに危険が伴う場合はその悪さもグレードに加算してある。いずれにせよ違った山域間のグレード比較は完璧ではないので、各エリア内ごとの標準ルートあるいは入門ルート等をもとに、各エリアのルートグレードを把握して欲しい。
グレードは絶対的なものではない。数字を盲信し、数字を追うことなく、くれぐれも謙虚なクライミングを心がけていただきたい。
夏、冬問わず、あるルートを他のルートと比べて困難度を云々するのは難しい。なぜなら、一口に“困難度”と言っても、どういう種類の困難度なのか、全く違った要素を同じ数字で比較することにまず無理があるし、仮に同じ要素を比べるにしても状況によって大きく変化してしまうことが多いからだ。特に冬のアルパインルートとなると、それは著しい。とはいえ、冬季アルパイン・クライミングという一つの分野の中で各ルートの困難度を比較しグレードを体系づける事は、自分の実力の把握や今後の目標ルートを選択する上で重要なことだろう。だが同時に、単なる数字へと単純化されたグレードシステムは、その真意を理解しない限り、大きな弊害となることは否めない。グレーディングに対する盲信、短絡的な自己評価、盲目的な高グレード追及などがそれである。本書の冬期グレード・システムを利用するにあたっては、くれぐれも表面化した一数字のみにとらわれず、その内容の真意を理解していただきたい。
さて、それでは冬期グレードに含まれる要素としては、どういうものがあるのだろうか。まず大まかに挙げてみると、
- 技術的な難しさ―――ピッチグレードやスケール、傾斜等。
- 取付きやすさ―――アプローチの長さや敗退のしやすさ等。
- 気象条件―――寒気その他の気象条件が登攀に与える影響。
- チャンスの得やすさ―――気象条件や外的危険に伴う登攀チャンスの頻度。
- 危険性―――確保条件、外的危険(雪崩、ツララの崩壊等。)などがある。
本書ではこれらの各要素を総合してグレードを付してある。もちろん全ての要素が低ければ総合グレードも低くなるし、全てが高ければ総合グレードも当然高くなる。問題はある要素に関しては困難度は低いが、他のある要素では高いというルートの評価である。例えば谷川岳・一ノ倉沢の滝沢スラブは、技術的には八ヶ岳の大同心正面壁より2~3ランクはやさしいが、チャンスの掴みにくさ、気象条件の悪さ、アプローチなどの要素によって、総合グレードは大同心より1ランク上になっている。だがこれらの要素が全て好条件に満たされれば、当然のことながら4級の滝沢スラブのほうが3級の大同心より楽に登れてしまう。といって条件が悪ければ、6級のルートをこなせる者でも手もつけられないといった場合もありうる。総合グレードはこれらの諸条件を、だいたい平均的に見て判断している。
グレードは絶対的なものではない。本書を利用するクライマー諸氏はそのことを念頭に入れ、謙虚なクライミングを心がけていただきたい。
冬期グレードの標準ルート
| 穂高岳 | 谷川岳 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 1級下 | 八ヶ岳・阿弥陀岳北稜 |
||
| 1級 | 八ヶ岳赤岳西壁主稜 |
||
| 1級上 | 東尾根 |
||
| 2級下 | 八ヶ岳・小同心クラック |
||
| 2級 | 一・二ノ沢中間稜 |
八ヶ岳中山尾根 |
|
| 2級上 | 前穂北尾根 |
一ノ倉沢四ルンゼ |
|
| 3級下 | 滝谷ドーム北壁 |
八ヶ岳・大同心正面壁 |
|
| 3級 | 一ノ倉沢中央稜 |
||
| 3級上 | 屏風岩東稜 |
一ノ倉沢南稜 |
|
| 4級下 | 滝谷クラック尾根 |
滝沢第三スラブ |
|
| 4級 | 滝谷P2フランケ |
烏帽子奥壁中央カンテ |
|
| 4級上 | 滝谷C沢右俣奥壁 |
烏帽子奥壁変形チムニー |
剣岳・チンネ正面壁 |
| 5級下 | 滝谷P2ジェードル |
幽ノ沢中央壁左フェース |
剣岳・八ツ峰Ⅵ峰Dフェース |
| 5級 | 剣岳・源治郎Ⅰ峰上部フェース |
||
| 5級上 | |||
| 6級上 | 奥鐘山西壁京都ルート |
||
| 6級 | 奥鐘山西壁広島ルート |
||
| 6級下 |
本書では、各ルートとその最難ピッチにグレードを付した。アイスクライミングのグレーディングは、その登攀スタイルとともに、可否および効果のほどは論議のあるところである。確かに同一ルートでも、12月と3月ではまったく状態が違ってしまうこともあるからだ。しかし、性格の似たルート間であれば、同一時期において、ルートやピッチのグレードを比較し、相対評価を下すことは可能と考える。
本書の性格はあくまでも、ルートガイドでありルート図集であるが、易から難へとクライミングをグレードアップしていくために、あるいは自己の実力に合ったルートを選択するための助けとして、ベストシーズンに登攀するという前提においてグレーディングを行った。したがって本書のグレードは参考グレードとし、現場でのルート状況の把握や判断を優先させて頂きたい。また本書のグレーディングは、各ルートの執筆者のグレード感覚によるもので、本書を作製するにあたって執筆者間で、グレーディングの細部にわたる統一はあえて行わなかったことも明らかにしておきたい。
アイスクライミングのグレーディングの諸要素にはどんなものがあるだろうか?大まかにいえば、①技術的困難度。②所要時間、高度差、積雪状態などの考慮。③確保条件。④ルートファインディング。⑤エスケープの可否。⑥アプローチ、下山路の条件。⑦自然条件地形、気象などがあげられよう。
そして非常に扱いの難しいものとして、氷の形状、性質およびその変わりやすさがあげられる。これは前記①~⑦の要素と重なり、深く関わっている。つまり、実際のクライミングで体に感じる難しさは、ピックに体重を預け、体を引きつけたりトラバースしたりする時の、微妙な感覚によって決まるということだ。たとえば、同じ傾斜のルートでも、氷質による体重のかけ方の微妙な違いで、感覚的には半~1グレード程度の相違が生じる。
このように氷のグレードというものは、非常に変動の激しい、とらえどころのないものだが、それにしても各ルートごとの難易の比較が必要なことは前に述べた。その場合は一応、各山域やルートの最良のコンディションを想定して、その上でグレーディングされるべきだろう。岩登りにおいて、乾燥した状態を基準にしてグレーディングがなされるのと同じ考え方である。そして形状や氷質などの変化によりピッチグレードは変動し、さらに天候条件全体がピッチのみならずルートグレードをも変えてしまうことがあるとの認識を持てばよいのだが、この点を理解しないと、Ⅳの氷瀑だからと登りに来て、悪い氷にあえなく墜落という破目にもなりかねない。
要は、グレードを鵜呑みにせず、その時々のルート状況を見きわめ、自分の実力に合ったラインを見つける、あるいはエスケープの判断を下す目を持つことが重要だ。
以上の考えを前提にあくまでも参考グレードとして表を作ってみた。ピッチグレードは前記①、③、④の要素、ルートグレードは①~⑦の全ての要素を計算するものとした。これには私およびその周辺の人間が登ったルートで、まあ大体このくらいかなという線を示しているが、本書のガイドの中にはまだ数登しかされていないルートも多く、そうしたルートでは多少高めのグレード付けがなされている可能性もある。また、各ルートのグレードはあくまでも相対グレードとして使う場合、同一山域内では比較的正当なものとなっていると思うが、違う山域、例えば甲斐駒と谷川岳の同一グレードのルートを登った時など人によってはかなりのギャップを覚えるだろう。
厳密な意味で垂直(体感ではなく形状的に)を対象としたアイスクライミングは、日本では80年代に始まり、その後多くのルートが登られたが、90年代に入り暖冬が続いていること、アルパインクライミング全体が低調なこともあり、多くの高難度ルートは数登を数える程度の状況である。高難度ルート間のグレード比較もアイスルートの場合、性格が違えば厳密にはとてもできるものではない。そういう意味で、本書の中にはガイドではあるが記録として読んでもらいたいルートも何本かあることを理解して頂きたい。
ピッチグレード
| + Ⅵ - |
荒川出合夢のブライダルベール |
非常に困難 |
|---|---|---|
| + Ⅴ - |
南ア甲斐駒七丈瀑 |
困難。 |
| + Ⅳ - |
中ア奥三ノ沢F1、正股沢大滝 |
バランスを要する。 |
| + Ⅲ - |
八ヶ岳ジョウゴ沢大滝 |
アンザイレンの必要あり。 |
| + Ⅱ - |
御在所岳二ルンゼ奥又右ルート |
手の補助、三点支持がいる。 |
ルートグレード
| 上 6 下 |
谷川岳一ノ倉沢烏帽子大氷柱 |
Ⅵ前後のピッチが連続する。 |
|---|---|---|
| 上 5 下 |
北ア丸山二ルンゼ |
困難なピッチが連続する。 |
| + Ⅳ - |
谷川岳幽ノ沢左方ルンゼ、南ア黄蓮谷左俣 |
困難な部分がある。Ⅳ程度のピッチが連続する。 |
| + Ⅲ - |
南ア戸台川本谷 |
短いが困難なピッチを含む。 |
| + Ⅱ - |
中ア正沢川幸ノ川 |
特に困難を感じず、条件もよい。 |
初心者
| コース難易度の内容 | 往復コース。 |
|---|---|
| 1日の歩行時間 および獲得登高差 |
歩行時間は3~5時間程度。獲得登高差約400mまで |
| 北海道エリア |
|
| 東北エリア |
|
| 信州・甲信越エリア |
|
| 東海・中ア・南アエリア |
|
| 近畿・関西エリア |
|
| 九州エリア |
|
初級
| コース難易度の内容 | 往復、周回、縦走コース |
|---|---|
| 1日の歩行時間 および獲得登高差 |
歩行時間は5~7時間程度。獲得登高差約400m~800m |
| 北海道エリア |
|
| 東北エリア |
|
| 信州・甲信越エリア |
|
| 東海・中ア・南アエリア |
|
| 近畿・関西エリア |
|
| 九州エリア |
|
中級
| コース難易度の内容 | 往復、周回、縦走コース。 |
|---|---|
| 1日の歩行時間 および獲得登高差 |
歩行時間は6~8時間程度。獲得登高差約800m~1000m |
| 北海道エリア |
|
| 東北エリア |
|
| 信州・甲信越エリア |
|
| 東海・中ア・南アエリア |
|
| 近畿・関西エリア |
|
| 九州エリア |
|
上級
| コース難易度の内容 | 往復、周回、縦走コース。 |
|---|---|
| 1日の歩行時間 および獲得登高差 |
歩行時間は7~9時間程度。獲得登高差約1000m~1500m |
| 北海道エリア |
|
| 東北エリア |
|
| 信州・甲信越エリア |
|
| 東海・中ア・南アエリア |
|
| 近畿・関西エリア |
|
| 九州エリア |
|
熟練
| コース難易度の内容 | 往復、周回、縦走コース。 |
|---|---|
| 1日の歩行時間 および獲得登高差 |
歩行時間は8時間以上獲得登高差約1500m以上 |
| 北海道エリア |
|
| 信州・甲信越エリア |
|
| 東海・中ア・南アエリア |
|
| 近畿・関西エリア |
|
- ※1.
- 「コースの難易度の内容」と「一日の歩行時間および獲得登高差」との組み合わせでコースグレードの1~5を決めている。山岳(ルート)によっては、組み合わせが異なることがある。
- ※2.
- 山中での宿泊日数(1日の行動区間)の設定は各社の判断による。
- ※3.
- 本表は、「ツアー登山運行ガイドライン」添付の「コース難易度(コース・グレード)及び引率者比率(ガイド・レシオ)」と関連しており、各エリアの具体的な山名(コース)を例示するにあたって、それに合致した歩行時間と登高差の目安をさらに表示した。
平成22年7月
一般社団法人日本旅行業協会/一般社団法人全国旅行業協会/公益社団法人日本山岳ガイド協会作成
ここでは、クライミングにおいて使われている、世界各国の主要なグレードを、それぞれ対応させて表にしました。
リードとボルダリングの違い、または国や地域ごとによる微妙な違いもありますが、大体はあっていると思われるので、参考にしてみてください。
ルートクライミンググレード対応表
| Decimal(アメリカ) | UIAA(国際山岳連盟) |
|---|---|
5.2 |
Ⅰ |
5.3 |
Ⅱ |
5.4 |
Ⅲ |
5.5 |
Ⅳ |
5.6 |
Ⅴ- |
5.7 |
Ⅴ |
5.8 |
Ⅴ+ |
5.9 |
Ⅵ-~Ⅵ |
5.10a |
Ⅵ+ |
5.10b |
Ⅶ- |
5.10c |
Ⅶ |
5.10d |
Ⅶ+ |
5.11a |
Ⅶ+~Ⅷ- |
5.11b |
Ⅷ- |
5.11c |
Ⅷ- |
5.11d |
Ⅷ |
5.12a |
Ⅷ~Ⅷ+ |
5.12b |
Ⅷ+ |
5.12c |
Ⅸ- |
5.12d |
Ⅸ |
5.13a |
Ⅸ~Ⅸ+ |
5.13b |
Ⅸ+ |
5.13c |
Ⅹ- |
5.13d |
Ⅹ |
5.14a |
Ⅹ+ |
5.14b |
ⅩⅠ- |
5.14c |
ⅩⅠ |
5.14d |
ⅩⅠ+ |
5.15a |
ⅩⅡ- |
5.15b |
ⅩⅡ |
5.15c |
ⅩⅡ+ |
ボルダリンググレード対応表※デシマルグレードとの対応表は、リードとの比較なので、注意。
| Decimal(アメリカ) | 段級グレード(日本) | V grade(アメリカ) |
|---|---|---|
5.2 |
||
5.3 |
10級 |
|
5.4 |
10~9級 |
|
5.5 |
9~8級 |
|
5.6 |
8~7級 |
|
5.7 |
7~6級 |
V0-,V0 |
5.8 |
6~5級 |
V0+,V1 |
5.9 |
5級 |
V1 |
5.10a |
5~4級 |
V1,V2 |
5.10b |
4級 |
V2 |
5.10c |
4級 |
V3 |
5.10d |
3級 |
V3 |
5.11a |
3級 |
V4 |
5.11b |
2級 |
V4 |
5.11c |
2級 |
V5 |
5.11d |
1級 |
V5 |
5.12a |
1級 |
V5 |
5.12b |
1級 |
V6 |
5.12c |
初段 |
V7 |
5.12d |
初段+ |
V8 |
5.13a |
二段 |
V8 |
5.13b |
二段+ |
V9 |
5.13c |
三段 |
V10 |
5.13d |
三段+ |
V11 |
5.14a |
四段 |
V12 |
5.14b |
四段+ |
V13 |
5.14c |
五段 |
V14 |
5.14d |
五段+ |
V15 |
5.15a |
六段 |
V16 |
※「アイスクライミング 全国版」「改定増補 アイスクライミング」「日本の岩場(上)(下)」 白山書房より抜粋